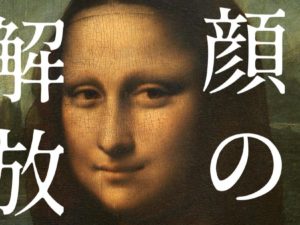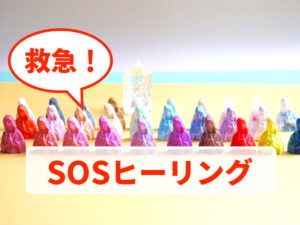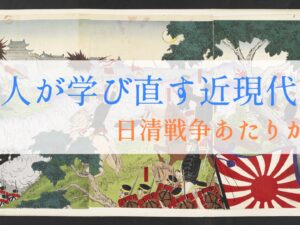こないだ友達がシェアしていたこれ!
気分超良くなるからちょっと見て〜〜〜〜〜〜
めったくそアガったわーーーーーーーーー。
このオバハン、ヴォーカルコーチの人、ものすんごいんだよ。オペラのアリア指導までできるんだもの。
アゲ方、ノセ方と、ダメ出し、軌道に乗せ方が絶妙だなと思った。プロよねえ。真のプロってものを見た思い。
そんでこれ以来、頭の中でホイットニーが歌ってる。
今日は朝っぱからから大音量で原曲かけてやった。
ねえ、つくづく、、、、、今、こういう曲ってないわーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ということでしみじみWhitneyについて考えるに、やっぱしデビューアルバムが一番よかった。
こんなに歌の上手い人出てきたのか!!!!って思った。
Whitneyのデビューアルバムと、日航機事故は同じ年だった。駿台に通ってたから御茶ノ水のディスクユニオンでLP買ったことまで覚えてる。
オバハン特有の、昔のことはよく覚えている現象。はーーーーーーーーっきり覚えているのよ。
とにかくこのジャンルは、ドナ・サマーとかダイアナ・ロスとかで、物心ついた時にはすでに大物だった。
そんな中に登場してきたのがWhitney
でも、そんな彼女も、真に良かったのは2枚目までで、そうこうしている間にマライアが出てきたので霞んでしまった。
そーだわマライアのデビューアルバムはCDで買ったんだった。
まじでビビった。鳥肌が立ったことを覚えている。
そんな中、90年代になって湾岸戦争真っ盛りの最中に行われたスーパーボウル(だったかな?)で
Whitneyが国歌斉唱して、湾岸戦争もスーパーボウルという舞台装置も、まあ、なんだかなあとは思ったものの、
そうは思っていながらも心震えて涙こぼれたのは忘れない。
この時ばかりはアメリカという国にに心底ジェラシーを感じたわ。
その後Whitneyは路線をチョイ変えして復活し、髪もクルクルじゃなくなり、ちょっと違和感があった。
軽快さよりは超絶技巧の曲調になり、「上手いんだけど退屈」と思うようになった。
だいたいもう、この頃からわたしは、ブラジルとかアルゼンチンとかポルトガルとかフランスとか
あるいはケルトとかの、マニアックな方角に行ってしまったからUSチャートで何が流行っていても関心なくなったんだった、、、、、
それに、声を張り上げる系の曲がすべて、重たく感じるようになったんだよね。
その後Whitneyは、、、、、あんな亡くなり方。
マライアも神格化され、わけわかんなくなっていき、今ではどん底からの這い上がりを「暖かく応援される」的な人になった。
ショービズって本当にねえ、、、、、、、
声という神から与えられたものを持つばっかりにね、本来神聖なものなのに「ビジネス」にされ、
楽しくもないのに笑わされ、
歌いたくもないのに歌わされ、
太っただの、奇行が目立つだの、落ちぶれただの、、、、、、
要するに莫大なお金を稼ぐがゆえに、短時間に消費されてしまうのよ。
「歌」は永遠なのにね、、、、、
ああ、そろそろ藤圭子の命日か。
ほなまた