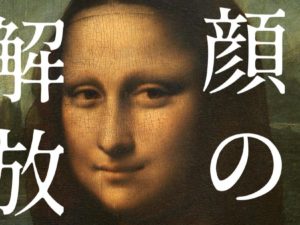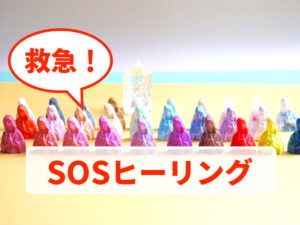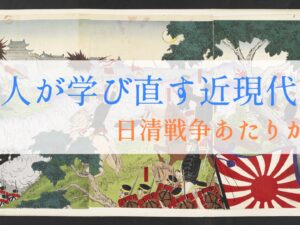前から楽しみだった映画『長崎の郵便配達』。
https://longride.jp/nagasaki-postman/
公開翌日に見てきた。
郵便配達をしていた少年の被曝体験と、生存体験の物語。贖罪の旅の途中で彼の存在を知った元英国軍パイロットとの交流の物語。そしてその父の著した本とともに、長崎の街を歩き、生前の両者の人生をなぞる娘とその家族の物語。
ものすごくしみじみと良質なドキュメンタリー映画。みんなにもぜひ見て欲しい。
「父と娘」ってやっぱり普遍的で特別なものだなと思った。父が娘に残すものと、母が娘に残すものは「違う」。どちらが良いとかではなく、種類が違う。父が娘に残すものは「でかい」んだよね。。。。
そして父が感じていた情感を「わかる」のは、妻ではなく娘という存在なのではないか、たぶんなぜなら、それこそが「血のつながり」(同様に母が感じる情感も、伝わるのは子供で配偶者ではないのではないか)。それが不可視のDNAというものだろう。
彼女にとって長崎が特別なように、わたしにとっても長崎は特別な町で、やはり父の足跡を辿る追体験をしているから、なぜか自分ごとのように深く感じ、涙がこぼれた。
ああ、長崎。また行きたいなあ。何度でも行きたいよ。
・・・・・なことを思っていたら、
昨日の深夜、NHKのドキュメンタリーで「長崎のお盆」をやっていたのを見てめちゃくちゃ心あたたまった。
先の映画にも出てきてびっくりしたのだが、長崎では新盆に「精霊船」という、本当に大きな、曳舟を作り道をゆく。
 そして爆竹を鳴らし、花火を上げる。新盆でなくとも花火はお墓でも一同揃って盛大に上げ、そのため市内の花火店箱の時期大忙しらしい。番組では、この花火を買い求める人たちが続々と、数十万単位で大量の花火をお買い上げしていく様子が写っていた。
そして爆竹を鳴らし、花火を上げる。新盆でなくとも花火はお墓でも一同揃って盛大に上げ、そのため市内の花火店箱の時期大忙しらしい。番組では、この花火を買い求める人たちが続々と、数十万単位で大量の花火をお買い上げしていく様子が写っていた。
もう一度言うけどその額、数十万だよ!
爆竹や花火は当然、中国文化からの影響が独自に発展定着したものだろうけれど、すーーーーーーーーごく素敵だと思った。
つまり長崎の人は、葬式と新盆、2回故人にお別れを言える訳で、お盆では花火という「一瞬にして消えるもの」にそれだけの額をかけ、派手にぶち上げたら故人も喜んでいるだろう、という考え方には、なんだかとっても揺さぶられた。
それから、妻や母親を亡くした男の人たちが、花火を上げながらはらはらと涙を流す姿にもグッときた。
男の人って、悲しくても寂しくても泣いたりできないのが常で、感情をしまっているじゃん。それがなんだか、素直に泣いてもいい時間、という風になっているのも非常に素敵なことだと思った。
また、みんなが爆竹鳴らして、大通りはまるで「ハロウィン後の渋谷」状態なんだけど、だから問題だ!みたいなことにはならないのも素敵だ。
なんというか、、、、、豊かな精神性を感じる。
隣の芝は青いという話じゃないよ。
ああ、、、、長崎行きたいな。